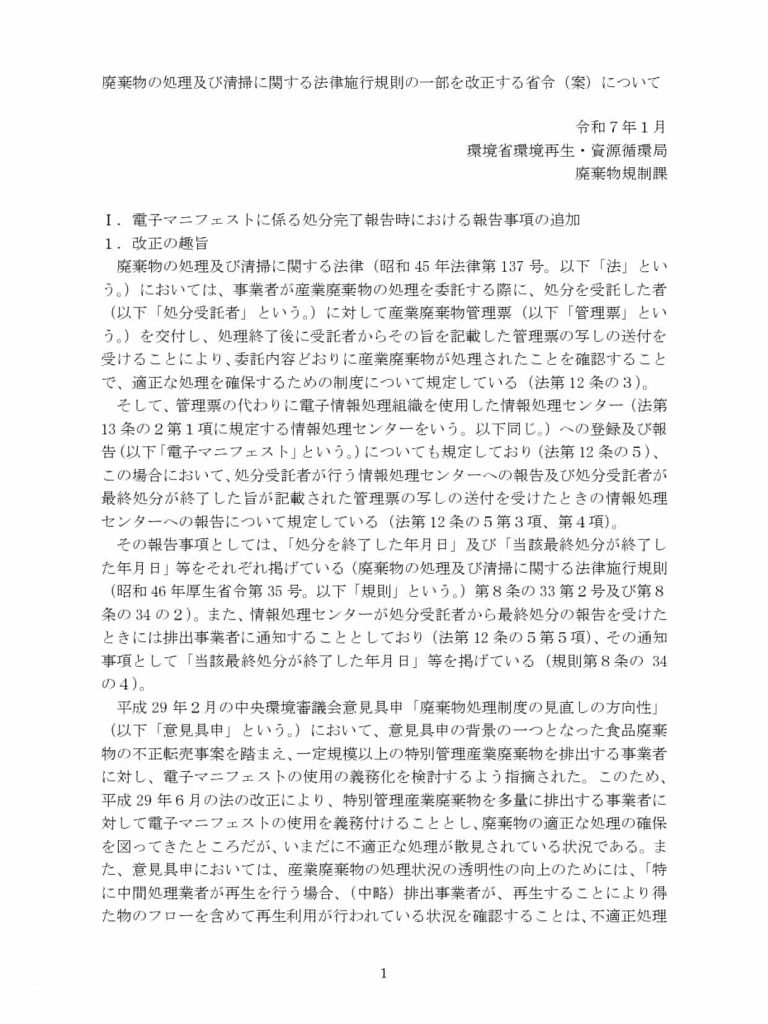リヴァックスコラム
第39回 「廃棄物処理法省令改正」について聞いてみよう その1
リヴァックスコラム愛読者の「むつご」さんから質問を受けました。
廃棄物処理法の省令が改正されると聞いたのですが、どういう改正になるのでしょうか?
はい。改正事項は3つあるようですが、うち1つは改正に伴う「条ずれ」の修正のようなので、実質は2つと考えてよいと思います。
1.プロローグ「条ずれ」
本題に入る前に、「条ずれ」ってなんですか?
たとえば、第6条に「○○○」と規定していて、第7条に「△△△」と規定していた。
改正で新第7条に「□□□」という規定を追加した時に、旧第7条の「△△△」という規定が押し出しをくらって新第8条になるって状況だね。
へぇ、そうなるとそれより後の第9条、第10条も一個ずつズレていくことになるんですか?
大抵は、それ以降の条を今までの通り使用するために、似たような内容の規定なら追加する規定を「第7条の2」のようにして、極力「条ずれ」を抑制しているみたいだね。
まぁ、BUNさんは法学を系統立てて教わった訳ではないから、条文制定のちゃんとしたルールはわからないけど。
なるほど。「の2」ね。便利な方法だよね。
そうとばかりも言えないんだよ。
廃棄物処理法は改正が多かったから、法律には「第15条の4の7」なんてあるし、省令に至っては「第12条の12の28」なんて条文まであるんだ。
適当な時期にガラガラポンして、枝葉はなくして欲しいって気持ちもあるなぁ。
2.電子マニフェストへの「再生量」の追加
さて、では、実質的な改正の話をしてくださいな。
一つは電子マニフェストへの「再生量」の追加と、これに付帯する事項もあるようだね。
ちょっと、詳しく一つ一つ解説してみてください。
まず、「電子マニフェストへの」ということは、紙マニフェストではこの追加改正は無いの?
理由はあとで説明するけど、今回の改正では電マニの場合だけ。
紙マニフェストでは「今までどおり」追加される項目は無し。
次に「再生量」ってことだけど、これは排出事業者が処理委託する時点では判らないよね。
そうだね。したがって、この追加項目が発生するのは受け手側になる処理業者だけ。
排出事業者の登録事項については「今までどおり」で、追加される項目は無し。
と、言うことは、今までのマニフェストシステムって紙マニフェストも含めて、受け手側の処理業者が記載や登録する事項って、「担当者名」や「処理終了年月日」程度だったけど、この改正以降は結構な事務量、業務量が出てきそうね。
そうだね。ちなみに今までも「担当者名」や「処理終了年月日」の他に「有価物を引き抜いたとき」は「拾集量」も記載、登録しなくちゃいけなかったけどね。
改めて、誰が、どんな事項を登録しなければならなくなるのか、確認させてくださいな。
処分受託者が、「処分方法ごとの処分量」及び「処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量」の報告、となるね。
たとえば?
そうだねぇ。
たとえば、解体工事から出た「木くず」100トンの処分を委託されたとしよう。
このうち、20トンは焼却炉で焼却。残り、80トンは破砕して、うち70トンは再生ボードとしてリサイクルできたけど、残りの10トンは埋立地で処分した、としようか。
この時、「処分方法ごとの処分量」は「焼却20トン」「破砕80トン」となる。「処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量」は「再生ボードとして70トン」「破砕残渣として木くず10トン」のようになるかな。
この項目を処分業者は電マニに登録しなくてはいけなくなるね。大変な業務量ですね。
慣れればそれ程のことも無いかもしれない。
どうして?
この再生量の登録に「当該処分量を的確に算出できると認められる方法により算出される処分量を含む。」というカッコ書きがあるでしょ。
たいていのリサイクル工場では処理工程は同じなので、リサイクル率もほぼ同じと想定される。
さっきの木くずの例だとすれば「80トン破砕すれば70トンは再生に廻せるけど10トンは使えず残渣になる」、すなわち70/80=0.875、リサイクル率87.5パーセントと想定できるから、余程状態が違ったケース以外は、過去の実績に基づいて受入量にリサイクル率を掛ければ自動的に数値は出てくるね。
それならその数字をパソコンに設定しておけば、受入量を入力するだけで「処分方法ごとの処分量」及び「処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量」も自動的に登録できるね。
でも、初期設定はそれなりの業務量だよね。
リサイクルする産業廃棄物の種類やリサイクルの手法、施設ごとにリサイクル率を設定しなければならないでしょう?
そうだね。たぶん、そんな準備期間も必要ということもあるんでしょうね。
1月の通知によれば、施行は令和9年4月1日と2年間の猶予期間を設定している。
この2年の間に処分業者と電子マニフェストを運用している情報処理センター(JW)の体制を整えてくださいねってことかぁ。でも、どうしてこんな改正をしたのかなぁ。
通知には今までの経緯や必要性等も記載しているけど、
実際には再資源高度化法をはじめとする世界、世の中の動きに呼応するためだと思う。
どういうこと?
今回の改正が電子マニフェストだけで紙マニフェストでは行われなかった、
ということを考えると、不法投棄等の不適正処理対策とは言いがたい。
そうだよね。不適正対応なら電マニも紙マニも差別する必要は無いものね。
まぁ、多くの良心的な中小零細、少量排出の排出事業者への負担を増やすわけにはいかないって要因もあるんだと思うけど、最大の要因はなんといっても「循環型社会形成」を推進していくための方策とそのバックデータの把握、これでしょうね。
なるほど。平成30年からは特別管理産業廃棄物の多量排出事業所は電マニが義務化されているから、この人達は既に電マニは導入されている訳だし、
再資源高度化法では年間1万トン、廃プラスチック類については年間1500トン以上排出する事業者は資源量の公表等も義務付けられているしね。
おっ、勉強してるね。
だって、リヴァックスコラム読んでるもの。
再資源高度化法なんて7回にもわたって連載したでしょう。
読者の皆さんでまだ読んでない方は、是非、バックナンバーも見てくださいね。
今までは、産業廃棄物は「適正処理」すればよかった時代。
でも、これからは「再資源化」が「義務」になる時代ってことだね。
それを排出事業者にも知ってもらうためには、自分が排出している産業廃棄物はどんな手法でどの程度再資源化されたかを知ってもらう必要があるし、日本全体としても今まで以上に再資源化を推進して、それを把握する必要がある。
それで、まずは取り組みやすい、電子マニフェストを使った部分からってことかぁ。
でも、そうなると電子マニフェストを使っている処分業者だけ負担が増えて、紙マニフェストしか使っていない業者と比較すると不公平じゃ無いの?
まぁ、いずれは全て電子マニフェストの時代となることを想定しているんだと思うけど、いくらかでも不公平感を無くす意味もあるんでしょうね。
「処分受託者による再生に係る情報の報告については、法第27条の2第10号の罰則規定は適用されない。」としている。
法定事項にはするけど、それをしていないとしても罰則の適用は無いってことね。
そうだね、そうしておかないと電子マニフェスト使用している業者だけがデメリットが大きくなるものね。
まぁ、社会への新たな制度の導入は、最初は「指導」、次に法制化、義務化だけど罰則なし、世の中に浸透して初めて「罰則」の適用とする流れが多いから、「過渡期」ってことかな。今回は長くなったのでもう一つの改正事項は次回ってことにしようか。
じゃあ、とりあえず、簡略的に今回のまとめをしてください。
・省令改正が行われ電子マニフェストの登録事項が一つ増えました。
・処分業者の「終了報告事項」として「再資源化」に関する事項です。
・施行は2年後の令和9年4月1日です。
と、言うことで関係する方々、特にリサイクル業者の方々は今後の対応が必要になりますのでアンテナ高くしておいて下さいね。